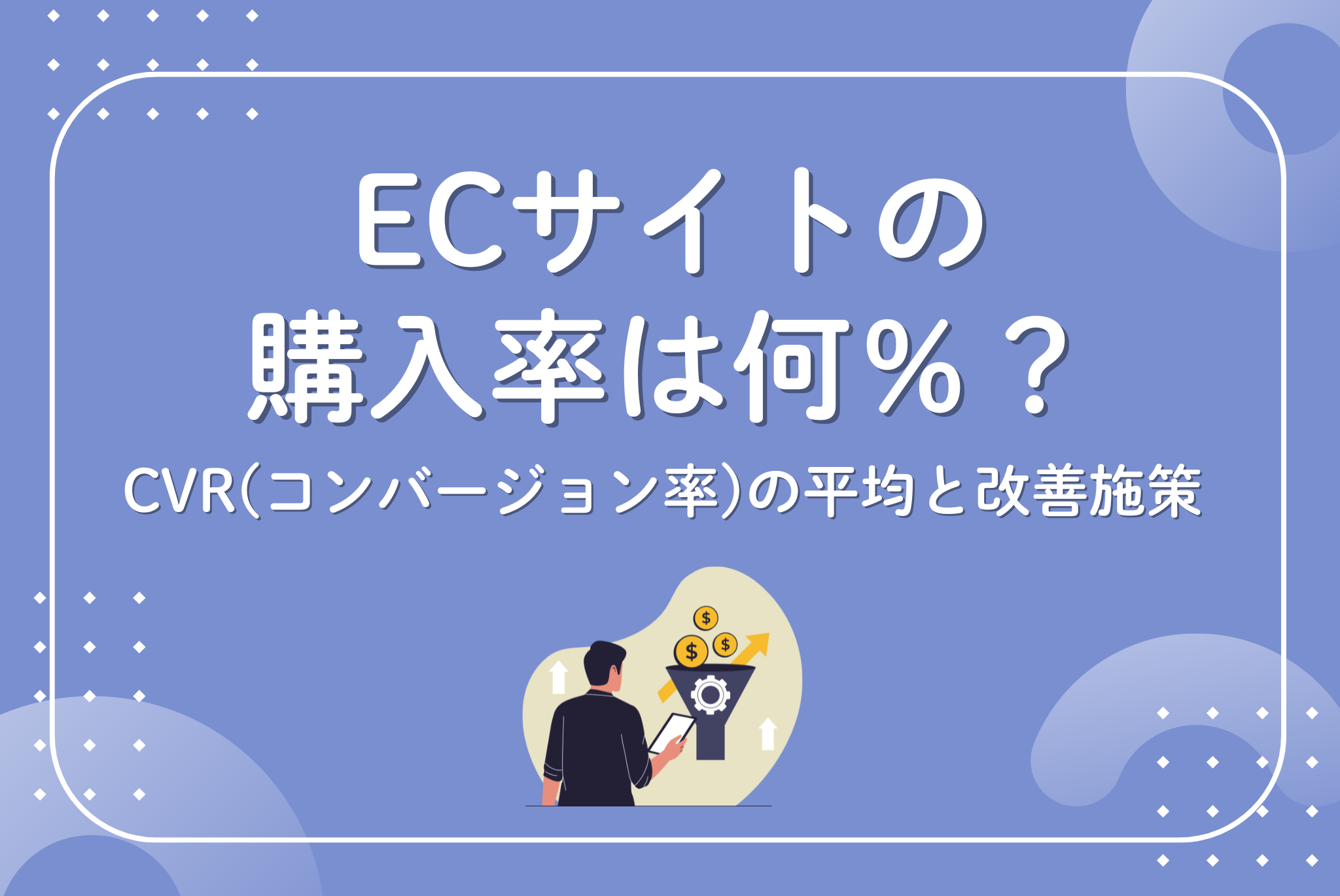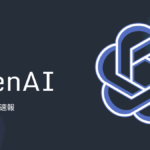100人来て2人買えばいいオフラインの接客とオンラインの接客(コンバージョン率の違い)
コンビニやスーパーに行くと、店に入った人のほとんどが何かしらを買ってレジに並びます。入店した人の9割がレジに並んで購入者になる──これがオフラインの世界の「コンバージョン率」です。
一方、ECサイトの世界ではどうでしょうか。
100人が訪問して、実際に自社ECで購入してくれるのは1〜2人。つまり購入率(コンバージョン率)は1〜2%の世界です。同じ「お店」でも、オフラインとオンラインではまるで前提が違うのです。
この数字だけ見ると「ネットショップって難しい」と感じるかもしれません。でも実は、ここにこそ“伸びしろ”があります。この「98人が買わなかった理由」を可視化し、少しずつ改善していくことが、ECの収益最大化につながります。
なぜECサイトは「100人に2人」なのか
まず、前提として来店目的がまったく異なります。コンビニは「買う前提」で入ります。のどが渇いた、コピーを取りたい、食べたい──目的が明確です。いつものお茶はないけれど、別のコンビニにいくには遠いし、ここで買っておこう。
一方ECサイトは、「買うかどうか」もまだ決めていない人が多く訪れます。欲しいものがなければ、実店舗と違い、クリックひとつですぐに別のお店にいくことができます。店員さんに気を使う必要もありません。
・なんとなくSNSで見た商品を調べている
・他社との価格を比較している
・使い方やレビューを見たい
・今すぐではなく“気になったからブックマーク”
このように、ECの来訪者の多くは「まだ検討段階」なのです。つまり、オンラインの世界では“お客様が迷っている状態から始まる”という前提を忘れてはいけません。
CVR(コンバージョン率)の計算方法
CVR = 購入者数 ÷ アクセス数 × 100
(例)100人来て2人買った場合
2% = 2人 ÷ 100人 × 100
GA4では「セッションのコンバージョン率」「ユーザーのコンバージョン率」の2種類があります。
「セッションのコンバージョン率」:コンバージョンが発生したセッションの割合
合計訪問回数のうち何件注文が入ったかを見ます。ECサイトの場合、リピート訪問やリピート購入も多いため、こちらを使うことが多いです。
「ユーザーのコンバージョン率」:コンバージョンに至ったユーザーの割合
何人来て、何人が買ってくれたかを表します。100人来て、買ってくれた人が2人(そのうちの1人は5回買っていてもコンバージョン数は「2」(2人)となります。顧客獲得数を把握したい時に使います。
CVR(購入率・コンバージョン率)の目安・平均
国内ECサイトのコンバージョン率の目安や平均は、公開されている数値は目安はあるものの公表されていることは少ないです。大手ECでも売上やアクセス数は公開されていても、コンバージョン率が公表されていることは少ないです。
業界や商品カテゴリーによっても様々で一概に何%ということは少ないのですが、1〜2%が平均値と思って差し支えないと思います。ご自身のECサイトのコンバージョンの参考にしてもらうために、私がこれまで見てきた中小の自社ECサイトで月商数百万円から数千万円規模のサイトのコンバージョン率の目安をまとめました。
BtoC 自社ECサイト
・食品EC(自社商品):2~3%
はじめてでも比較的試しやすく、CVRは高い。お中元、お歳暮時期に上がる傾向。
・雑貨EC(仕入商品):1~2%
衝動買いしやすく、商品やキャンペーン企画次第でCVRは左右される傾向
・アパレルEC(仕入れ商品):0.5~1.5%
ウィンドウショッピングを含めて何度も見てアクセス数が増えるためCVRは低くなる傾向
・家具EC(自社商品):0.5~1.5%
ソファなど大型家具の場合、比較検討期間が長く低くなる傾向
BtoB 自社ECサイト
・業務用EC:4~5%
業務で必要に迫られた目的買いのため、在庫や価格、納期が合えば購入率は高い
・建材EC :3~4%
必要な型番、メーカー
・会員制EC:10%以上も
購入するためにアクセス、ログインするため、CVRは高い
モールと自社ECでは「来店目的」が違う
楽天やAmazonなどのモールでは購入率が3〜5%と自社ECよりも高い傾向にあります。
なぜならユーザーは「買う目的」で来ているからです。「楽天市場で靴を探す」「Amazonでマウスを買う」いわばモールは“巨大なショッピングセンター”であり、購買意欲の高い人が集まる場所です。
一方、自社ECサイトは「ブランドや商品を知ってもらう入口」でもあります。検索やSNS、広告から初めて訪れる人も多く、購入目的よりも情報収集や比較検討が中心。
そのため、サイト内での“接客”が非常に重要になります。
オフラインでは店員が笑顔で「いらっしゃいませ」と声をかけ、お客様の反応を見て商品の説明やおすすめを変えています。オンラインではそれを画面上で再現する必要があります。
オンラインでの「接客」とは何か?
ECサイトにおける“接客”とは、「ユーザーが次に何をすればいいか」を迷わず理解できるようにすることです。
たとえば──
・商品ページに「こんな人におすすめ」と具体的な使い方を載せる
・レビューやお客様の声を見やすく配置する
・送料や発送日を明確に伝える
・初回購入者向けのクーポンをポップアップで案内する
・カートボタンを目立たせ、購入完了までのステップを最短にする
これらはすべて、実店舗での声かけ・提案・案内にあたります。「サイトの中でどう接客するか」を設計できているかどうかが、1〜2%の世界で“売れる店”と“見られるだけの店”を分ける分岐点です。
「接客導線」を意識する
EC改善を行う際、よく使う言葉が「接客導線」です。これは、“お客様がどの順番でページを見て、どんな気持ちの変化を経て購入に至るか”を設計する考え方です。
たとえば以下のような流れです。
商品一覧 → まずは「見た目」と「価格」で興味を引く
商品詳細 → ストーリーや特徴で「欲しい理由」を作る
レビュー・FAQ → 不安を解消して「安心感」を与える
カート → 支払い・配送情報を簡潔にし「離脱させない」
こうした流れを1ページずつ丁寧に整えるだけで、購入率は確実に上がります。実際、BtoC自社ECサイトで接客導線を整えることで1.8%→3.5%へと倍増した例もあります。
「100人に2人」ではなく「2人が買ってくれた理由」に注目する
つい「98人が買わなかった」と考えがちですが、実は「2人がなぜ買ったか」にこそ改善のヒントがあります。
・どのページを経由して購入に至ったのか
・どんなデバイス(スマホ/PC)からか
・どの広告・投稿を見て来たのか
・どの商品画像・レビューが決め手になったのか
これらのデータをGA4やヒートマップで追うと、成功パターンが見えてきます。成功した導線を他の商品ページにも展開すれば、購入率全体を底上げできます。
「リアル店舗の温度」をどうオンラインで再現するか
これは、私自身がインテリアショップの実店舗の販売担当からネットショップ担当になった時に試行錯誤したことでもあります。リアル店舗では、照明・香り・スタッフの声・陳列など、五感すべてで「買いたくなる空気」をつくっています。ECサイトでも同じです。
商品の世界観やブランドの温度をどう伝えるか。写真のトーン、言葉の選び方、レビューの見せ方──そのすべてが“オンラインの空気づくり”です。
私が考える「オンライン接客」の理想は、「顔の見えない中でも、温度を感じるサイト」です。機能的なECではなく、ストーリーのあるEC。買って終わりではなく、ブランドと長く関わりたくなるような体験。これこそが、中小ECサイトが大手に勝てる最大の強みです。
1〜2%をどう伸ばすか
1%の購入率を1.2%に上げるだけでも、売上は20%増えます。100人中、2人が買っていたお店が3人になれば、売上は1.5倍です。小さく見える数字が、実は利益を左右するほどのインパクトを持っています。アクセスを増やすことも大切ですが、「来てくれたお客様をどれだけ大切にできるか」。オンラインでもリアルでも、商売の本質は変わりません。
100人に2人買ってくれればいいというECサイトの世界。だからこそ、その2人が「また買いたい」と思える体験を積み重ねていきましょう。それが、“愛されるEC”への第一歩です。
ECサイトのコンバージョン率アップを目指してお困りのことがありましたら、
ぜひOMOKAJIまでお気軽にお声がけください。
一緒に、“愛されるEC”を目指していきましょう!!