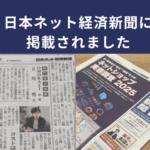- MIT NANDAチームの最新報告書が、従業員による生成AI利用の普及を示唆。
- 企業側の正式なAI導入は依然として不十分。
- 95%の企業で生成AIの試行プロジェクトが失敗。
- 従業員の90%以上が個人用AIツールを業務に利用。
MITのNANDAチームが発表した報告書によると、生成AIの従業員による利用は急増しているが、企業としての公式導入はかなり遅れている。
「The GenAI Divide: State of AI in Business 2025」と題されたこの報告書によると、多くの従業員がITの承認なしに個人用AIツールを業務に活用している。これを「シャドーAI経済」と呼び、従業員はChatGPTやClaudeといったツールを日常的に使用している。
驚くべきことに、95%の企業で試行中の生成AIプロジェクトが失敗し、顕著な利益への影響が見られない。公式なAIイニシアチブは、大型言語モデル(LLM)がワークフローから学ぶ能力に乏しいため、進展が遅れている。
しかし、個々の利用者にとっては、これらのツールが十分に柔軟で効率的であることが報告されている。シャドーAIは公式イニシアチブよりも高い投資収益率を示すケースが多い。また、調査対象の40%の企業が正式なLLMサブスクリプションを購入したにもかかわらず、90%以上の従業員が個人用AIツールを業務で活用していることが明らかになった。
多くの企業では、従業員が何度もLLMに頼る一方で、公式プログラムは試行段階のままだ。この動向は、柔軟で応答性の高いツールが導入のギャップを埋める可能性があることを示唆している。
企業は、このシャドー利用を研究し、どこで効果があるのかを測定し、正式なツールの導入に役立てようとしている。このアプローチは、個人利用と公式導入のギャップを解消する手助けとなるだろう。
報告書は、LLMがしばしば文脈を忘れ、学ばず、適応しない現実とリンクしている。人間は、重要な仕事の90%を好み、一方でAIは迅速なタスクには高い評価を受けている。専門家は、AIをブレインストーミングや初稿作成に役立てる一方で、繰り返しエラーを起こすという意見も示している。
このように、シャドーAIの影響は静かな形で様々な作業の担当者を変えつつある。企業にとっては、この個人用の利用を正式な形で安全に取り入れることが重要である。
適切なガバナンスがあれば、シャドー活動は公式な実践として承認される可能性がある。正式なツールが学び、適応するまでの間、実用的な成果は個々のAI利用や小規模なワークフローの変更から得られる。

えっと、生成AIってそんなにみんな使ってるの?
でも、企業が導入するのは遅れてるってどういうことなんだろう?
やっぱり新しいツールにはリスクがあるのかな?
それとも、何か使い方が難しいのかな?
はい、ユータさん。
生成AIは多くの従業員が利用していますが、企業側は正式に導入するのは遅れています。
これは、社内のガイドラインやセキュリティの問題が影響しているからです。
新しいツールのリスクや、従業員が使いやすい方法を模索しているのかもしれませんね。
企業が個人の利用を研究して、正式に取り入れることが大切です。


実際、生成AIの利用が急増しているという報告が出ていますが、企業側の公式な導入はなかなか進んでいない状況です。
多くの従業員が、ITの承認なしに個人用のAIツールを活用していることを考えると、いわゆる「シャドーAI経済」が生まれています。
その一方で、95%もの企業での生成AIの試行プロジェクトが失敗しているというのは驚くべき事実です。
企業が新しいツールのリスクを避けながら、導入に向けた一歩を踏み出すのは容易ではありません。
しかし、従業員が個人のAIツールを使うことで得られる柔軟性や効率性を企業側も意識し、正式な導入に向けた研究を進める必要があります。
このギャップを埋めることが企業には求められているのです。